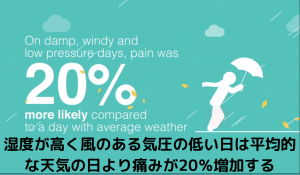次々と明らかになってくる腸内細菌叢の破壊がもたらす原因不明の病気

次々と明らかになってくる腸内細菌叢の破壊がもたらす原因不明の病気。
原因が不明とされてきた、パーキンソン病発症の原因が「抗生物質による腸内環境の破壊」である可能性がフィンランドの研究で分かった。
パーキンソン病もこのブログでも何度か取り上げてきた病気のテーマですが、このパーキンソン病も発症の原因が分からない病気として、様々な研究がされている病気の一つだと思います。
改めて、パーキンソン病というのはどういう病態かと言うと、
手足の震え、こわばり、歩行困難などを伴う進行性の神経疾患で、脳のド-パミンという神経伝達物質が減少することによって起きる病気のこと。
しかしなぜ、ド-パミンが減少するかは謎でした。
今回の研究で、抗生物質を多く摂取(投与)された人達にパーキンソン病が明らかに増加したことが分かった、という報告です。
私たちの身体の中に必要な様々な神経伝達物質が作られますが、その神経伝達物質を作っているのが腸内に住む細菌によってであることが、ここ最近の研究で明らかになってきています。
それらを産生している腸内細菌が「抗生物質によって破壊される」ことで、必要な量の神経伝達物質を作り出す事ができないために、発症している可能性が高いという報告です。
抗生物質の服用はパーキンソン病増加のリスクと関連があることを発見

ここからです。
フィンランドのヘルシンキ大学病院の研究者によって発表されたこの論文は、ムーブメント・ディスオーダー誌(Movement Disorders)の最近号に掲載された。
この研究は、抗生物質の服用とパーキンソン病のリスクとの関連を発見したというもので、腸内細菌叢に対する抗生物質の影響によるものである可能性を示唆した。
調査結果はまた、抗生物質にさらされてから、パーキンソン病の症状の出現するまでの間に最大15年もの時間が経過した可能性があることも示していた。
最も強く関連が有った抗生物質はマクロライド系とリンコサミド系だった。これらの抗生物質は通常医師が感染症に対するものとして一般的に処方されるものである。
以前での研究は、パーキンソン病に典型的な腸の変化が診断される以前のはるか昔、20年前に起こりうることを発見していた。
過敏性腸症候群、便秘、炎症性腸疾患などの腸の症状がある人は、パーキンソン病のリスクが高くなる。
ヘルシンキ大学病院の神経科医、フィリップ・シェペルジャン博士(Dr. Filip Scheperjans)は、以下のように述べている。
「抗生物質への曝露とパーキンソン病の関連は、パーキンソン病の典型的な症状が発症する何年も前に、かなりの割合の患者でパーキンソン病の病態がおそらく腸内細菌の変化に由来する可能性がある、という現在の見解に合致しています」
「この発見は、将来の抗生物質を処方する慣行にも影響を与える可能性がある」と付け加えた。
パーキンソン病と腸
パーキンソン病は、運動を制御する脳の一部にある黒質のドーパミン細胞を殺すが、この細胞の損傷によって、一般的にはからだの硬直、震え、バランスを崩すなどの症状を引き起こす。さらには、うつ病、気分変化、睡眠障害、皮膚の問題、便秘、排尿困難など、他の症状も発症する場合がある。
パーキンソン病の症状は通常、発症するのに何年もかかり、人によって症状が異なって進行する。
パーキンソン財団によると、世界中で約1,000万人がパーキンソン病にかかっているが、米国においては、毎年約60,000人がパーキンソン病と診断されている。
腸内微生物の変化と、多発性硬化症、自閉症、統合失調症、うつ病、パーキンソン病などの脳の状態との関連性を見つける研究が増えている。
しかし、腸内微生物の変化が実際にこれらの状態を引き起こすのか、それとも単に付随するだけなのか、についてまだ多くの討論が必要だ。
抗生物質とパーキンソン病の最初の研究
シェペルジャン博士と彼らの研究論文では、初期のパーキンソン病患者の腸内微生物の変化を観察し、抗生物質が微生物の個体数に長期的な影響を与える可能性があると指摘している。
しかし、それまで、抗生物質への曝露とパーキンソン病のリスクとの間に直接的な関連があるかどうかを実際に調査した人はいなかった。
そこで、彼らはこのギャップに対処するために、フィンランドの全国的な医療データを使用して症例対照の研究を実施した。
国家登録から、チームは1998年から2014年の間にパーキンソン病の診断を受けた人々を特定することができた。また、1993年から2014年にかけて、国内のデータベースを使用して経口抗生物質を個別に購入した。
次に、これらのデータに統計的手法を適用して、以前の経口抗生物質曝露とパーキンソン病との関連性を調べた。
この分析では、パーキンソン病の診断を受けた13,976人の抗生物質暴露と、パーキンソン病ではなかった40,697人の対照の抗生物質暴露を比較した。同じ性別、同年齢や同じ居住地に住むパーキンソン病の人と比較した。さらに、投与量、化学組成、作用機序、および抗菌範囲に従った抗生物質の暴露についても分類。
さらに、調査結果を確認する必要がある
この結果は、マクロライド系とリンコサミドへの暴露がパーキンソン病のリスクと最も関連があることを示している。
分析はまた、パーキンソン病と診断される15年前までの抗嫌気薬とテトラサイクリンのパーキンソン病のリスク増加への関連を明らかにし、また、診断される5年前までには、スルホンアミド、トリメトプリム、および抗真菌薬への関連もあった。
将来の研究でも同じ結論に達した場合には、パーキンソン病の感受性における増加は、医師が抗生物質を処方するとき、それらの潜在的な危険リストも加えて考慮する必要があると考える。
「抗生物質耐性の問題に加えて、抗菌薬の処方では、腸内細菌叢および特定疾患の発症に対する潜在的で長期にわたる影響を考慮する必要があるでしょう。」
―フィリップ・シェペルジャン博士
ここまでです。
マクロライド系抗生物質
抗生物質としては比較的副作用が少なく、抗菌スペクトルも広い。ことにリケッチア、クラミジアなどの細胞内寄生菌や、マイコプラズマに対しては第一選択薬となる。小児から老人まで広く処方される頻用薬の一つであるが、一方ではその汎用性が一因となってマクロライド耐性を示す微生物が増加しており、医療上の問題になっている。また、他の薬物との薬物相互作用が問題となる場合もある。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
便利・安心・清潔の世界に潜む健康リスク
1928年にアレクサンダー・フレミングが偶然、青カビから見付けたペニシリンが世界初の抗生物質でした。
その後、たくさんの抗生物質が生まれ、様々な感染症から人類を救ってきました。
しかし最近では、その抗生物質に対して耐性をもつ菌(ウィルス)が現れてきて問題にもなっています。
ところが、いまでも病院に行けば、内科や歯科、耳鼻科、皮膚科などでも、かなり乱用気味に処方され続けています。おそらく我々すべての大人は、もうすでに過去に何度も抗生物質を服用しているはずです。多分一度も抗生物質を飲んだことはない、というひとは(日本にいる人に限れば)存在しないと思います。
もちろん、服用した量や頻度によってその抗生物質による腸内環境の破壊は程度の差こそあれ、まったく被害がなかった人はいないでしょう。
過去多量に服用し続けた人もいるでしょうし、そういった人の腸内環境はかなり悪化しているでしょうし、一旦破壊された腸内環境は、基本的には元に戻ることはありません。
「せめて、今の子供達には抗生物質の投与はできる限り慎重に行うべき」だと考えます。